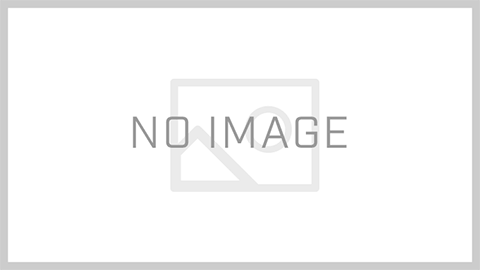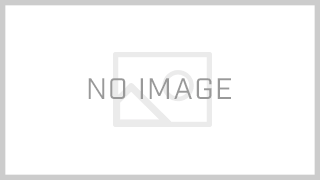・問題を印刷して、単語リストを見ながら解答する。
・↓で訳を確認しながら再度読む。
・答え合わせ(正解は一番下)
{ }⇒前の名詞を修飾している部分
< >⇒名詞節(「~ということ」という意味のまとまり)
①、②、③…⇒andやorでつながれているもの
全部はつけていない。難しい部分のみ。
※自分で読むときには記号をつけない方がよい⇒間違えるから。
※訳はAI。
True or false: ‘The Eiffel Tower is in France.” Most of us can quickly and accurately answer this question by relying on our general knowledge. But what if you were asked to consider the claim: “The beehive is a building in New Zealand.” Unless you have visited New Zealand or watched a documentary on the country, this is probably a difficult question. So instead of recruiting your general knowledge to answer the claim, you’ll turn to your intuition. Put another way, you’ll rely on what Stephen Colbert calls “truthiness” ― truth {that comes from the gut, and not books}.
「エッフェル塔はフランスにある」は本当かうそか.私たちのうちほとんどの人は,一般知識を頼りに素早く,そして正確に.この問いに答えることができる.しかし、次のような主張について考えるように求められたらどうだろう.「ビーハイブは.ニュージーランドにある建物である」ニユージーランドを訪れたり.この国に関するドキュメンタリーを見たりしたことがない限り.おそらくこれは難しい問越である.したがって,この主張に答えるために一般知識を使うのではなく。直感を当てにすることになる。別の言い方をすれば。スティーブン=コルバートがいうところの 「本当らしさ」,つまり。文字で記された記録ではなく、直感による正しさに頼ることになるのである。
As a cognitive psychologist, I study the ways that memory and belief go wrong: How do we come to believe that things are true when they are not? How can we remember things {that never actually happened}? I am especially fascinated by the concept of truthiness ― how smart, sophisticated people use unrelated information to decide whether something is true or not.
認知心理学者として,私は記憶や信念がどのように問違ってしまうかを研究している。どのようにして,本当はそうではないのに物事が真実だと私たちは信じるようになるのだろうか。どのようにして。実際にはまったく起きていないことを思い出せたりするのだろうか。私はとりわけ,本当らしさという概念に興味がある。賢くて教養のある大たちが。あることが真実であるかどうかを判断するのに,どのようにして無関係な情報を使うのか、ということである。
For instance, in a classic study by Norbert Schwarz and Rolf Reber at the University of Michigan, people were more likely to think <a statement was true> when it was written in high color contrast (blue words on white) as opposed to low contrast (yellow words on white). Of course, the color contrast has nothing to do with <whether the claim is true>, but it nonetheless biased people’s responses. The high color contrast produced a feeling of truthiness in part because those statements felt easier to read than the low color contrast statements. And it turns out that this feeling of easy processing (or low cognitive effort) brings with it a feeling of familiarity. When things feel easy to process, they feel trustworthy ― we like them and think they are true.
たとえば,ミシガン大学のノーバート=シュワルツとロルフ=リーバーによるある古典的な研究では,文章がコントラストの弱い色(白地に黄色)ではなく,強い色(白地に青色)で書かれている場合のほうが,人はその文章を本当であると考える傾向が強かった。もちろん,色のコントラストはその文章が真実かどうかとはまったく関係がなかったが,それでも,そのコントラストが人々の反応を偏らせたのだ。コントラストの強い色が本当らしいという感じを生み出した理由の一つは。その文章が色のコントラストが弱い文章よりも読みやすく感じられたことである。そして,処理が簡単である(つまり,認知の努力が少ない)というこの感覚は。親近感をもたらすことがわかっている。物事が簡単に処理できると感じられると,信頼できると感じられ,私たちはそれを好み,本当だと思うのである。
In my research at UC Irvine, I have collaborated with psychologists in New Zealand and Canada to discover the ways we can be tricked into thinking that something feels familiar, trustworthy and true. In our studies, we have focused on how photos and names can have surprisingly powerful effects on our memories, beliefs and evaluations of others.
カリフォルニア大学アーバイン校での私の研究では,ニュージーランドとカナダの心理学者たちと共同で,大はどのようにだまされて。あることを知っている,信頼できる,本当だと感じると考えてしまうのかを調べている。私たちの研究では,どのようにして写真や名前が,人の記憶や信念や他人への評価に驚くほど強力な影響を及ぼすかに焦点を当ててきた。
Photographs can boost comprehension and make it easier for us to learn and remember new information. But cognitive psychology research shows that photos can also have a negative influence ― they can lead us to believe and remember things are true when they are not. In a study by Elizabeth Loftus and others at UC Irvine, people {who saw a doctored photo of President Obama shaking hands with the former Iranian president Mahmoud Ahmadinejad} actually said they remembered the event happening ― even though it was completely false. Photos can even trick us into remembering false events from our own childhood. People {who saw a doctored childhood photo} came to remember a false event (riding in a hot air balloon) with the same detail and emotion {that you would expect from a real memory}.
写真は理解を促進し,新情報を知ったり記憶したりするのを容易にしてくれる。しかし,認知心理学の研究では。写真はまた,マイナスの影響も持ちうることがわかっている。写真は。物事が真実ではないのに,真実だと大に信じさせたり思い出させたりすることがあるのだ。カリフォルニア大学アーバイン校のエリザベス=ロフタスらによる研究では。オバマ大統領が元イラン大統領のマフムード=アフマディネジャドと握手をしている偽造写真を見た人たちは,現に,その出来事が起きたことを覚えているといった。それがまったくのうそであるのにもかかわらず,である。写真は,私たちをだまして。自分自身の子ども時代のうその出来事を記憶していると思わせることさえある。孑・ども時代の偽の写真を見た人たちは,実際にはなかった出来事(気球に乗ったこと)を,本当の記憶なら期待できるであろう詳細さと感情とともに、思い出すようになった。
Photos are a record of real events, so it’s not surprising that we often view them as the best evidence that something actually happened. <What is more surprising> is our recent work {showing that photos can alter our beliefs even when they do not provide any evidence for the claim at hand}. In a study {we conducted in New Zealand at Victoria University of Wellington}, we found that when people read a statement (such as “Macadamia nuts are in the same evolutionary family as peaches”) alongside a decorative photo {that simply related to the claim (a bowl of macadamia nuts)}, they were more likely to believe that the claim was true. That is, these decorative photos produced truthiness ― photos {that were related to but did not depict the claim} encouraged people to believe that the claims were credible. .Moreover, this truthiness effect persisted over days, not minutes, and could have long-lasting effects on people’s beliefs.
写真は現実の出来事の記録なので,私たちがそれを何かが実際に起きたといういちばんの証拠だと見なすことが多いのは驚くには当たらない。もっと驚くべきことは,写真は,今目の前にある主張の何の証拠にもならないのに、人の考えを変えてしまうことがあると、私たちの最近の研究が示したことである。私たちがニュージーランドのビクトリア大学ウェリントン校で行った調査で、人々がある文(たとえば「マカダミアナッツは,桃と同じ進化的類縁関係にある」)を,その主張と単純な関係しかない装飾的な写真(ボウルに盛ったマカダミアナッツ)とともに読むと,その主張が本当だと信じる傾向がより強かったことがわかった。つまり,こうした装飾的な写真が本当らしさを生み出したということである。主張と関連はあるが,主張そのものを表現してはいない写真でも,人々がその主張は信頼できると思い込むことを促したのだ。しかも,この本当らしさの効果は,数分ではなく,何日も続き,人々の考えに長期にわたる影響を及ぼす可能性があった。
But visual cues are not the only source of non-diagnostic evidence {that people use to evaluate claims}. People can be influenced by even more subtle features of information, like the linguistic attributes of a word.
だが,視覚的なきっかけは,人がさまざまな主張の評価をするのに使う,判断には役立たない情報源として唯一のものではない。人は,ある言葉の言語的な属性といった,情報のもっと微妙な特徴にさえ影響されることがある。
We know that pronunciation can influence our judgments about products, stocks and activities. Put simply, people prefer things {that are easy to pronounce}. We think that Magnalroxate is a safer food additive than Hnegripitrom. We think that the roller coaster {called Ohanzee} is less risky than the one {called Tsiischili}. And in the stock market, easy-to-pronounce ticker codes (KAR) perform better than their difficult-to-pronounce counterparts (RDO) ― even after just one day of trading.
発音が、製品や株,さまざまな活動に関して、人の判断に影響を及ぼすことがあることはわかっている。簡単にいうと,人は発音が簡単なもののほうを好むのである。私たちは,マグナロクセイト(Magnalroxate)のほうが,ネグリピトロム(Hnegripitrom)よりも安全な食品添加物だと思う。オハンジー(Ohanzee)という名のジェットコースターのほうが。チースキリ(Tsiischili)という名前のジェットコースターよりも危なくないと思う。そして、株式市場では、発音の簡単なティッカーコード(たとえばKAR)のほうが,発音の難しいティッカーコード(たとえばRDO)よりも,ほんの1日の取引後でさえ、業績がよいのである。
It is one thing for pronunciation to influence perceptions of products, amusement park rides and stocks. Surely we don’t let such an irrelevant cue influence our ideas about another person?
発音が,製品や遊園地の乗り物や株の認識に影響を及ぼすのは一つの事実である。しかし,私たちはきっと他人をどう思うかについては,そのような無関係なきっかけにおめおめと影響されたりしないのではないだろうか?
But it turns out that we do. People {who have easier-to-pronounce names} are thought to be safer, less risky and more familiar. We give them more votes than their counterparts with difficult-to-pronounce names. We even use the pronunciation of a person’s name as a source of information to evaluate the credibility of his or her claims. In our most recent study, we asked people to evaluate the truth of a series of statements ― half were attributed to someone with an easy-to-pronounce name, and half were attributed to someone with a difficult-to-pronounce name. We found that when the claims were paired with easy-to-pronounce names, people were more likely to think they were true. People believed the claim ‘Turtles are deaf” more when it was attributed to “Andrian Babeshko” than when it was attributed to “Czeslaw Ratynska.” The easy names produced truthiness.
ところが、実際には影響されてしまうのである。発音しやすい名前の人は、より安全で、危険ではなく,親しみやすいと思われる。そうした人には、発音の難しい相手よりも票を入れてしまうのだ。私たちは,人の名前の発音を,その人の主張の信頼性を評価する情報源として使うことさえある。最近の研究で,私たちは一巡の発言の正しさを判断するように被験者に求めたが、その発言の半分は名前の発音が簡単な人のもの,もう半分は名前の発音が難しい人のものとした。明らかになったのは。主張が発音の簡単な名前と組になっている場合のほうが,人はそれを正しいと考える傾向が強かったということだ。人々が「カメは耳が聞こえない」という主張を信じたのは,「アンドリアン=バベシュコ(Andrian Babeshko)」によるものとしたときのほうが,「チェスラウ=ラティンスカ(Czeslaw Ratyns-ka)」によるものとしたときよりも多かった。簡単な名前が本当らしさを生み出したのである。
Of course, the pronunciation of a name or a loosely related photograph should have no influence on people’s judgment of truth. So why do they influence our judgments? Like the high-color contrast statements, claims {attributed to those with an easy name or those accompanied by a photo} feel easier to process. The easy names require less cognitive effort; a photo helps people to visualize and understand a claim more rapidly. This feeling of easy processing is often taken as a sign <that information is familiar, credible and true>. To the primitive parts of our brains, that feeling of familiarity signals something {that we can trust}, while information {that’s difficult to process} signals danger.
もちろん、名前の発音や、関係性があまりない写真は、真実に関する人々の判断に何の影響も与えるべきではない。では、なぜ、そうしたものが私たちの判断を左右してしまうのだろう。それは、色のコントラストが強い文章と同様に、簡単な名前の人物のものとされる主張や、写真を伴う主張は、処理するのが簡単だと感じられるからである。簡単な名前は認知上の努力が少なくてすむ。写真は、主張を視覚的にとらえて理解するのをより速くしてくれる。処理が簡単だというこの感覚が、多くの場合、その情報がなじみがあり、信用でき、本当であるという印として受け取られるのだ。人の脳の原始的な部分にとっては、なじみがあるというその感覚が、信用してよいものだという合図となり、一方で、処理するのが難しい情報は危険の合図となる。
This feeling of familiarity could influence us in a variety of contexts. In the courtroom, an easy name might make a witness or expert seem more credible. In the workforce, an easy name might help an individual’s resume float to the top of a stack. And in the news, a photo ― even one {that is only loosely related} ― might make a story seem more credible.
なじみがあるというこの感覚は,さまざまな状況で私たちに影響を及ぼしうる。法廷では,簡単な名前が証人や専門家をいっそう信頼できると思わせるかもしれない。労働者集団の中では,簡単な名前の人の履歴書はいちばん上に置かれるかもしれない。そして、ニュースでは、関係性が少ししかない写真でも,それは報道をより信用できるものと思わせるかもしれない。
So how can we avoid being taken in by a false sense of truthiness? Cognitive psychology research has shown that people are often unaware of ①their biases or ②<how information influences their judgments>. But simply being warned about the influence of names and photos might just make us a little more cautious ― leading us to look for truth {that comes from books, and not the gut}
では,私たちはどのようにして,本当らしさという間違った感覚にだまされることを避けられるだろうか。認知心理学の研究は,多くの場合、人々は自分の先入観や,情報が自分の判断にどのように影響しているかについて気づいていないことを明らかにしている。しかし,ただ名前や写真の影響について警告されるだけでも、人はもう少し注意深くなるかもしれない。つまり、直感ではなく文字で記された記録による真実を求めるようになるかもしれない。
解答例
1.ある文章が色の対比がはっきりした文字で書かれていると,情報処理の容易さから人はその内容を信じる傾向が増すこと。(60字以内)
2.
①理解や記憶の一助となる一方で、誤ったことや偽りの記憶を真実・事実と思い込ませたりする。(45字以内)
②写真は通常,現実の出来事の記録であるため,偽造写真でも偽の記憶を喚起し,ある陳述と関係はあるが証拠にはならない写真でも,陳述内容を正しいと思わせるものとなる。(80字以内)
③発音しやすい名前の商品や人物のほうが,信用できるという印象が強い。(35字以内)
3.なじみのある名前なら,法廷では証人や専門家は信用されやすく、仕事では履歴書が目に留まりやすい。また、ニュースでは関連の薄いものでも写真があると信頼されやすい。(80字以内)
4.情報を処理するのが容易であるために,直感的に信頼でき,真実であると人に思わせるものが発する印象。(50字以内)
5.名前や写真が物事の真偽に関する私たちの判断に及ぼす影響を知り,直感に頼らず,文書で真実を求めること。(50字以内)
.